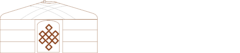モンゴルでお茶と言えば乳入りのスーティツァイ(乳入りのお茶)、カザフではアクチャイ(白いお茶)が定番です。乳は馬以外の家畜たち(ラクダ、ヒツジ、ヤギ、ウシ)たちのものが利用されます。茶葉はモンゴル国内では栽培されてないので、基本的に交易で手に入れることになりますが、茶葉がないときには、それぞれの地域で植物の葉や茎、花などを煮出したものを飲用していました。森に近いところではローズヒップを煮出したりもします。
カザフにせよ、モンゴルにせよ、お茶は特別なものと見なされていますが、お湯を沸かし、茶葉を入れて、最後に乳を入れるに際し、「乳に混ぜ物をして薄めるのはダメなのよ」と言ったり、乳がないときに「ごめんなさいね、黒いお茶で…」などというように、乳が入っている方がより上級のものとして扱われます。乳の方がお茶よりも格が上と考えられているようです。
観察してみると、モンゴルのツァイ(茶)という言葉は茶葉もしくはそれに準ずるもの(植物の葉や茎など)が入っている“温かい飲物”を指しているかもしれません。これに対して肉の入っている場合にシュル(汁・スープ)と言い分けているのか?とも思ったのですが、残りものの餃子に温かいお茶をかけたバンシタイツァイ(餃子入りお茶)というお茶?スープ?もあります。どういう理解で境界線があるのか?大いに興味のそそられるところです。



お茶を入れるのは女性の仕事とされていて、結婚式の時には新婦が新居のストーブに火をともし、お茶をいれて振る舞うことが重要な儀式の一つになっています。
また地域や家によって入れる塩の量はかわりますし、キビなどを入れたり(南モンゴル地域に多い)など様々な飲まれ方があります。ヤクやトナカイの乳は濃厚で溶けにくいため、鉱塩(モンゴル語でホジル)で溶かしてから茶に加えるなどします。カザフ人たちは、モンゴル人たちよりも比較的濃くお茶を煮出して、サルマイ(有塩バター)を浮かべるなどします。更に、モンゴルではヒーツティツァイ(穀物入りお茶)をおもてなし茶と言って出すことがあります。穀物をバターなどで炒り、そこに水をいれてお茶にした香ばしい濃厚なお茶(?)です。
現地ではこれらお茶に揚げパンやチーズ、クリームなどを入れて飲む?食べる?ことも多いです。一つのお碗に、その時々でいろんなものを入れる日常の“お好み飲料”が遊牧民のお茶です。お茶を入れている最中にその家を去ってはいけないだとか(作法があります)、飲み残してはいけないなどの様々な作法もあります。