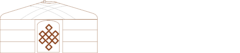店長の西村幹也です。
NPO法人北方アジア文化交流センターしゃがぁの理事長として活動を続けてきましたが、「なぜ、モンゴル?」と聞かれることがとても多いので、簡単にではありますが、まず、それについてのべたいと思います。
どこかの土地のエキスパートになりたい…。その土地で見聞きしたことを伝えるジャーナリストになりたいというのがはじめの一歩でした。似たような顔をしている人々のいるアジア地域がいいなと思い、続いて、暑いところは苦手だなとおもったところで、中国、朝鮮半島、モンゴルしか選択肢は無くなりました。関わっている人が少ないところの方が面白そうだなと思った時点で、もはやモンゴル語をまずは身につけようって思ったわけです。

大学入学後、シャーマニズムに興味を持ち、文化人類学を専攻し、1991年に中国の内モンゴル自治区に留学したのがモンゴルと本当の意味で深く関わるきっかけです。1989年6月4日の天安門事件のあと、中国国内の諸民族は様々な形で民族文化を奪われ続けているのですが、自分たちが苦しい状況にあるそんな社会情勢下にあったにも関わらず、異邦人である私の留学を温かく迎え入れてくれたのがモンゴル人たちでした。研究者になるかどうかなんてわかりもしない、何も知らない若者に自分たちが大切にしてきた様々を惜しげもなく分け与え、「俺たちモンゴル人は、50年もしたらきっとモンゴル語も話せなくなり、遊牧文化もなくなってしまうんだと思うよ。でも、モンゴル国には兄弟たちがいて、彼らが誉れ高きモンゴルの名を後世に残してくれるんだ。お前も、俺たちのことをちゃんと伝えてくれよ」と涙ながらに語る友人たちの思いにどのように応えたらいいのだろう?と思わずにはいられませんでした。
当時、自分自身もモンゴルのことをまだまだ知らないことだけは確かでしたから、とにかくモンゴルのことを深く学ぼうと進学し、見聞きしたことをできるだけ多くの人に伝えようと決め、そこから後は、とにかく、時間が許す限りモンゴル人の住む土地に通うようになって、今に至ります。
そして、現地で見聞きしたことを伝えるために、モンゴル情報紙しゃがぁを創刊。その後、NPO法人化して以降、各種イベントを全国で開催、小学校での馬頭琴体験会などを含めた講演・公演回数は1000回を超えます。
2012年にはこれら地道な活動がモンゴル国に認められ、友好勲章を授与されることとなりましたが、これはひとえに活動を支援してくださったたくさんの方々、そして、私にたくさんのことを教えてくれた遊牧民の方々のおかげだと思っています。

活動を継続していくための資金繰りをしていくなかで、遊牧民雑貨店をNPO法人事務局のある北海道京極町に作り、全国各地で移動販売をしてきました。
そんな流れの中で、新しい活動拠点を作りたいなと思い立ち、このたび、色々な縁やワケがありまして、岡山に手作り雑貨とカフェの店しゃがぁを2025年1/4に開店する運びとなりました。
別に遊牧文化に限った活動をするつもりはなく、全国各地で、何かに本気で取り組んでいる素晴らしい方々との出会いがありましたが、そのような繋がりをここに持ち込みながら、様々な人々がそれぞれの個性を持ち寄って、互いにインスパイアされあって、新しい何かを創出する、ハブスポットのような場所にしたいと思っています。
かつてのシルクロードのオアシス都市にあった広場が、私のイメージです。あちらこちらから、色々な人やモノが集まってきて、それぞれがそれぞれの個性(当時においては言語や宗教はそれぞれがそれぞれのまま)を尊重し合って、互いに影響を請け合い、個々の文化を更に発展させていったのがオアシス都市の広場でした。この時代に、世界史が出来上がったのだというのは岡田英弘先生の言ですが、コロナ禍時代に分断されてしまったモロモロを今一度、つなぎ合わせられたら、そのつなぎ目になれたら…というのが私の願いです。
”しゃがぁ”とはモンゴル語で、”くるぶしの骨”を言います。モンゴル遊牧民はこれをたくさん集めて大切にしますが、これは豊かさを象徴します。1頭から2個しか取れないくるぶしの骨がたくさんあるということは、家畜に恵まれていることを示すからです。日本とモンゴルの関係が豊かなものになるように、また、そのためのジョイント・つなぎ目になれたらと言う願いを込めて法人名をしゃがぁとしています。ですから、当法人の活動は、とにかく人々を集めて、つなぎ合わせること、そしてそのときに必要な知識や経験を共有することなのです。
新しい店舗、”手作り雑貨とカフェの店しゃがぁ”が、みなさんとみなさん、文化と文化のつなぎ目となれますよう、みなさんのお力添えをお願いしたいと思っています。
どうぞ、今後とも、よろしくお見知りおきのほどをお願い申し上げます。
西村幹也

学歴・職歴
東京外国語大学モンゴル語科卒業
モンゴル情報紙しゃがぁ編集室代表 1994年~2008年
東京外国語大学地域文化研究科博士前期課程修了
総合研究大学院大学文化科学研究科比較文化学専攻博士後期課程満期退学
国立民族学博物館外来研究員 2002~2003年
大阪学院大学非常勤講師(文化人類学)2002年~2004年
帯広大谷短期大学専任講師 2006年~2009年
NPO法人北方アジア文化交流センターしゃがぁ理事長 2008年~
大阪大学非常勤講師 2021年度~
北海道民族学会会員
北海道立北方民族博物館研究協力員
留学歴
1991年1月~7月 中華人民共和国内モンゴル自治区内蒙古師範大学
1992年10月~1993年9月 モンゴル国国立民族大学
1997年4月~1998年3月 モンゴル国国立外国語大学
刊行書籍・論文・抄録
2018 研究ノート 「モンゴル国タイガ地域のモンゴル化とトナカイ乳利用の変化 ―西タイガ地域の事例報告」『北海道民族学第 14 号』
1995 「ホブスゴル 精霊と語る人々」「モンゴル式結婚の宴」他、計7テーマ 18 頁『モンゴルまるごと情報局』トラベルジャーナル社
1997 「ボーの宗教」の復活-シャマニズム」『アジア読本 モンゴル』pp.230-237 河出書房
1997 「復活する伝統宗教」『草原の遊牧文明 大モンゴル展によせて』pp.64-67 財団法人千里文化財団
1998 「モンゴル西北部フブスグル地域のウリヤンハイ人とシャマニズム」『第六回大阪アジアスカラーシップ活動報告書』pp.51-66
1998 「ツァータン」「ダルハド」各項目『世界民族事典』」弘文堂
2000 「いまどきのモンゴル人結婚式レポート」『ワールドカルチャーガイド 中国』pP158-161 トラベルジャーナル社
2001 「幻の魚を追って奥地の川へ」他、計 23 テーマ 58 頁『ワールドカルチャーガイド モンゴル』」トラベルジャーナル社
2003 「自然と人間のあるべき姿を学ぶ-モンゴルの草原と森での生活から-」『北方民族博物館友の会季刊誌 Arctic Circle 44 号』
2003 「モンゴル北部ダルハド盆地のシャマニズム ツァータン・トバの事例」『東西南北 和光大学総合文化研究所年報』pp.87-101.
2003 「ポスト社会主義時代におけるトナカイ飼養民ツァータンにおける社会適応-モンゴル北部タイガ地域の事例」pp.45 ~ 58
『スラブ・ユーラシア世界のおける国家とエスニシティ』JCAS Occasional Paper no.15.2003 帯谷知可/林忠行編
2004 「モンゴルの家畜と人の関係 -家畜飼育の方法から探る-」『北方民族博物館友の会季刊誌 Arctic Circle 55 号』
2004 「ツァータンの生活と文化」北海道立北方民族博物館第 19 回特別展『北の遊牧民 モンゴルからシベリアへ』図録解説
2004 「トナカイ飼育における群管理と馴化技術-モンゴル北部ツァータンの事例- 抄録」『北海道民族学会会報』第2号
2007 「在日モンゴル人」 『2007 年版現代用語の基礎知識』
2008 「トナカイ飼育民ツァータンの年間移動とトナカイ管理」『帯広大谷短期大学紀要 45 号』
2009 『もっと知りたい国 モンゴル』心交社
2011 「タイガの春」『北方民族博物館友の会季刊誌 Arctic Circle 80 号』
2011 「草原の祭 – ナーダムの競馬 -」『北方民族博物館友の会季刊誌 Arctic Circle 81 号』
2011 「『北方民族博物館友の会季刊誌 Arctic Circle 82 号』
2011 「タイガの元旦」『北方民族博物館友の会季刊誌 Arctic Circle 83 号』
2012 研究ノート「トナカイ飼育民ツァータンの生活変化 – 金に翻弄されるタイガ社会 -」『北海道民族学第 8 号』
2017「モンゴル国のカザフと馬」『第 32 回特別展図録 ユーラシア北方のウマ牧畜民 カザフ モンゴル サハ」北方民族博物館
活動歴は…しゃがぁ公式サイトをご覧下さい